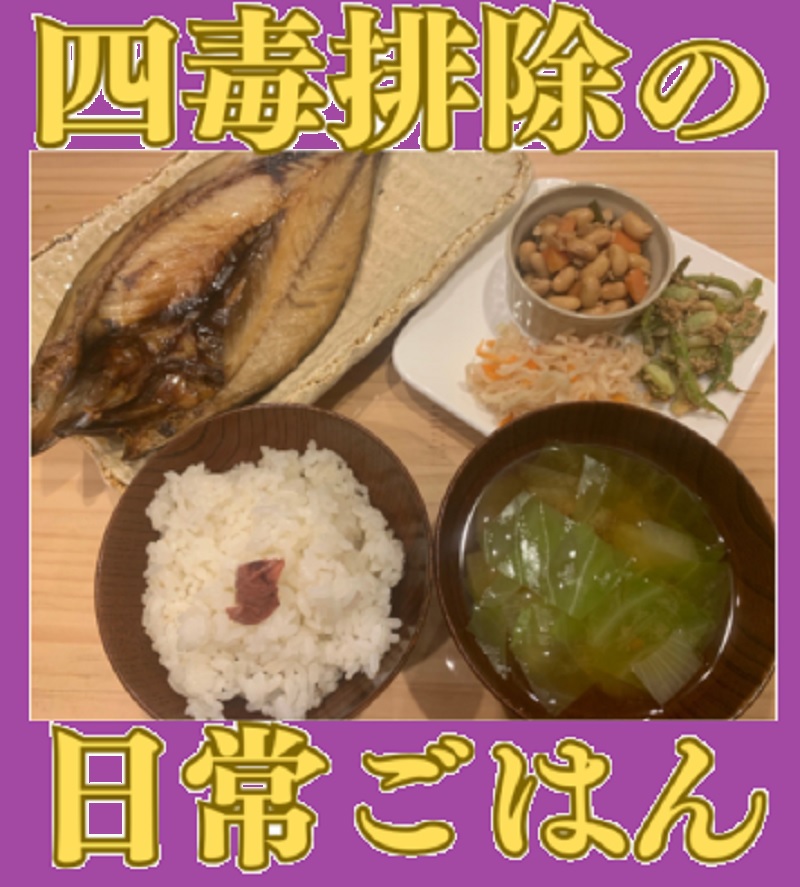食い物は大事、かなり大事。
最近、四毒抜きという言葉を良く聞く。
吉野先生が言い出したことで、別段それ自体はいいんだけど、僕はなんか違和感を覚えてて(笑)
四毒とは、「小麦、植物油、乳製品、甘いもの」のことらしい。これらを抜くことで不定愁訴的な病だけでなく、原因がはっきりしている病も抑えられる食事法ということ。
んー、なんだかつまらない食事だなぁと、個人的には思う。
小麦はグルテンが腸内で悪さするという。
確かに小麦のグルテンは他にはあまり存在しない特殊なタンパク質であり、難消化性で、腸内環境を悪化させて様々な病気を引き起こす。
まぁ、別段これに関して反論はない。
ただ、1万5千年前から栽培されていた小麦。諸外国では主食ですらある。
日本ではというと、弥生時代から存在していて、栽培もしていたらしい。
一般的に言われる日本人の7割がグルテン不耐症なら、なぜそんなものをそんな時代から栽培していたのだろうか。
僕が思うのは、グルテンが身体に合わないとなってきたのは、実は近年ではないかと思う。
小麦の品種改良によりグルテン過敏症の発症原因であるグリアジンの量が40倍に増えたのがその理由。
なんでも、便利に簡単にと進化させると、だいたい身体に悪いものに変わっていく。
セリアック病に関しては、グルテンというよりも、おそらくだけど、収穫前除草剤か遺伝子組換え食品に含まれるBtタンパク質が原因。
つまり、悪者は小麦そのものではなく、行き過ぎた人間の欲望(笑)。
僕はパン屋を開業していた時期があるが。無農薬で栽培した古代小麦のパンならば問題が起きなくなる例は沢山あった。
つまり、品種改良や栽培方法が問題ということなのだから、除外ではなく選択のほうが大事と言う話。
次に植物性油脂はと言うと、リノール酸(オメガ6系脂肪酸)が問題となっている。それと熱による酸化かな。
それ自体も別段反論はない。
しかし、リノール酸は体内で生成はできないし、身体には必要な必須脂肪酸でもある。
問題となるのは過剰摂取ではなかろうか。そんなに沢山摂取するような食事自体が問題なのである。
油の使いすぎ(笑)。そもそも日本の伝統的な料理は油をそんなに使わない。
使うとしたら天ぷらだろうけど、あれはポルトガルから伝わった嗜好品。本来、たまに食べるもの。
オメガ6とオメガ3、オメガ9のバランスがと考えるのは、あくまでも油にどのくらいオメガが含まれているかを調べることができる技術があるから。
人はそうした技術を知ると、それを信仰したがる癖がある。
日本が縄文時代から栽培していたのはエゴマである。エゴマは油として使われていたし、猪の脂は溶けにくく重宝していた。
つまり、これも除外ではなく、選択が大事。
三つ目は乳製品。ガゼインが問題と言う。これに関しても理解できる。
α-カゼイン、β-ガゼイン、Κ-ガゼインのうち、人間の乳には少ないα-ガゼインが多過ぎるのが問題。
カゼインは単体で存在するわけではなく、カルシウム−カゼイン−リン酸複合体の形で存在していて安定しているが、確かに消化は難しいし、腸には良くない。
しかし、人類の多くは動物の乳をミネラル源として利用してきた歴史がある。牛乳を直接飲むのは確かに不耐性もあり問題があるのは分かるが、なぜバターまで敵にするのか。
バターにはカゼインはほとんど含まれてはいない。
それよりも、僕が問題と思うのは飼育方法である。成長ホルモン、抗生物質、ワクチン。理由を作れればなんでもありだ。
カゼインが悪いとか言う話をする前に、これも除外ではなく選択。
甘いものに関しても言いたいことはあるが、もう長くなったからいいや(笑)。
僕個人の意見で言えば、成分を悪者にするその考え方は、結局飼育方法や栽培方法の問題点を隠してしまうから好きじゃない。
元々は、飼育方法や栽培方法の問題から提案されたのかもしれないけど、四毒抜きだけ伝わって広がってるのが、僕にはなんとも心地悪い。
できるだけ自然に、できるだけ美味しく、できるだけ安全に飼育し、栽培しようとしている人たちまで、その煽りを食っている。
改善して欲しいのは、消費者側の食ではない。食を供給する生産側である。
もちろんこれは僕個人の考えであり、僕のこの考えが正しいとは限らないが、なんだか物事の本質から外れていくのは嫌だなぁと思う。
どの商品を選択するのか。それが消費者の最も簡単な意思表示であり、世の中を変えるための一つの方法である。